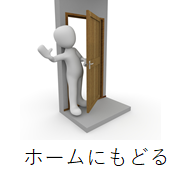ガソリンが安いというと、「そんなことはない。高いぞ!」という声が聞こえてきそうだ。しかし、ガソリンはコンビニで売られているミネラルウォーター、つまり水より安いのだ。まず、ガソリンには高額な税金(揮発油税53.8円と消費税17円、その他、石油税など)が掛けられているから、それを差し引くと100円前後となる。一方、ミネラルウォーターはスーパーでは100円前後で売られているので、ガソリンはミネラルウォーター、つまり水と同じくらいの値段で売られているということになる。
ミネラルウォターの原料は井戸などからくみ出した水だから一応、タダ (土地の購入料あるいは租借料、固定資産税などもあるかもしれないが、変動費べースの費用はポンプの電気代くらいだろうか)。その井戸水からゴミなどをろ過し、加熱殺菌したあと、ペットボトルに詰めて完成だ。
一方、ガソリンの原料である原油は取引市場で価格が決まり、現在60ドル/バレル程度。これをリットルに換算すると55円くらいになる。その原油を何千kmも離れた中東から運んできて、製油所で様々な工程を経て精製し、さらに国内を輸送してガソリンスタンドで販売する。このような複雑な工程を踏んでいるにもかかわらず、締めて税抜き100円で売られている。いや原料費(原油代)を差し引くと45円。水より安い。そう考えると、ガソリンがなぜこんなに安くできるのか不思議に思えてくる。
なぜだろうか。それは、徹底した自動化と大規模化の貢献が大きいといえるだろう。
1.自動化
輸入された原油は、まず蒸留という操作によって、LPG、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油、重油といった中間製品におおざっぱに分けられる。そのあと、ガソリンは脱硫や改質によって品質が整えられたガソリン基材というものになる。ただ、それだけでは、旺盛なガソリン需要にはぜんぜん足りない。そこで、多くの製油所では分解装置という設備を使って重油からガソリンを作っている。
そのほか、スイートニング装置や重合装置、アルキレーション装置、ベンゼン回収装置、コーカーなど様々な装置によって、いろいろな種類のガソリン基材が作られ、最終的にはそれらを適切な割合で混合して、自動車燃料として適切な性能を持った製品となって出荷される。
このように何種類も精製装置を使っててガソリンは作られるわけであるが、その工程はきわめて複雑である。しかし、これらの装置は自動化されており、一旦動き始めると、ほとんど人間が与せずに1年365日、24時間、ずっと連続的に動き続ける。運転員は生産計画に合わせて装置の処理速度を増やしたり、減らしたりすることはあるが、それ以外は装置が順調に動いているかどうかをチェックするのが主な仕事となる。(事故やトラブルがあると忙しくなるが)製油所では自動化によって人件費が徹底的に抑えられているのである。

また、中東から原油を輸入するのに使われるタンカー(VLCC)は全長400mに達する巨体であるが、この船はわずか20名ほどの乗組員で操作されている。もちろん、タンカーも24時間走り続けているわけであるから、乗組員は3交代制がとられており、常時タンカーを動かしているのは7名ほどでしかない。たったこれだけの人数で、この巨大な原油タンカーを動かしているのだ。
このように徹底した自動化によって、従業員数を抑え、かつ24時間体制で夜間や休日でも連続して稼働させることによって、人件費やその他の経費を抑えているわけである。
2.大型化
タンカーや精製設備を大型化することもコストダウンの有力な手段だ。例えば一日1万バレルの原油を処理できる製油所を2万バレルに拡張したとする。原油の処理量は2倍になり、ガソリン生産量も2倍になるが、手間は同じであるから同じ人員数で操業することができる。つまり、ガソリン1リットルあたりの人件費は2分の1になる。
もちろん、設備を大型化すれば、その設備の建設費は大きくなるが、処理能力が2倍になったからといって、設備の建設費が2倍になるわけではない。0.6乗則といって、だいたい0.6乗倍(1.52倍)になるといわれている。ということで、製油所やタンカーなどは大きければ大きいほど1リットルあたりの製造コストが低減できるということになる。
この結果、世界の製油所はどんどん大型化していった。我が国でも5万バレル以下の小規模な製油所はどんどん閉鎖されていき、現在19か所ある日本の製油所は、最小でも7万バレル、最大の製油所は35万バレルもある。
ただ、大型化には問題もある。大型化した以上は、その設備をフルに活用しなければならないことだ。たとえ超巨大な精製設備を作ったとしても、その設備で生産されたガソリンが、例えば半分しか売れなければ、精製能力の半分は無駄になる。
その結果、石油会社はできるだけ大量のガソリンを売ろうとするから、競争が激しくなり、競争に勝とうとするから、販売価格を下げざるをえない。こういうこともガソリンの値段が安い原因になっているのだ。
そのほかにもさまざまなコストダウンの努力が行われている。例を挙げると、綿密な生産計画を立てることや、石油会社間のバーター取引などである。
3.綿密な生産計画
ガソリンの製造工程は既に述べたように非常に複雑で、さらに製油所ではガソリンだけでなく灯油やジェット燃料、軽油、石油化学製品なども同じような複雑な工程で製造され、しかも、これらの製品は互いに関連しあっているから、あちらを立てればこちらが立たずという関係が複雑に入り混じっている。しかも、最終的には消費者がほしいという量の製品をきちんと作らなければならないし、一部の製品が余ったから廃棄するということも許されない。
その関係をうまく整理する方法としてLPモデルという手法が使われている。これは製油所運営上のさまざまな制約条件を数千から数万という一次方程式で表し、その中で最もコストダウンが見込める解を得るという方法である。もちろんコンピューターでなければ、この巨大な連立方程式を解くことはできない。しかし、これよって最終的に最もコストの安い、あるいは収益が最も大きい製油所の操業が行われ、石油製品全体のコストを下げることが可能になっている。
4.バーター
石油会社どうしでガソリンをやり取りすることをバーターという。製油所が大型化し、小型製油所が閉鎖されていくと製油所の数が減って、製油所から消費者への輸送距離が伸びてくることになる。
例えばA社が北海道に、B社が九州に製油所を持っていた場合、A社が九州でガソリンを売ろうとすれば、北海道から九州までガソリンを運ばなければならない。逆にB社が北海道でガソリンを売るときは九州から北海道に運ばなければならない。それなら、A社は九州でB社からガソリンをもらって販売し、北海道ではB社がA社からガソリンをもらって販売すれば、A社、B社とも輸送コストを大幅に削減することができる。
このように石油会社間でガソリンの貸し借りを行うことをバーター(製品交換)と呼んでいる。石油会社は製油所を大規模化することによって、織烈な販売競争を行っているわけであるが、一方で互いに製品を融通しあってコストダウンに努めているというわけである。
そもそも、企業は利益を上げることが目的の組織である。そのためにはできるだけ生産コストを下げて、かつできるだけ高い値段で売る必要があり、それ以外に方法はない。利益を上げるため、各石油会社はできるだけ生産コストを下げる努力をしているが、一方で競争が激しい業界であるから、高い値段で売ることは難しい。ということで、消費者には安い製品が提供できるというわけである。ただし、これは公正な競争が行われた場合でだという、ただし書きがつくことになるが。
2025年10月9日