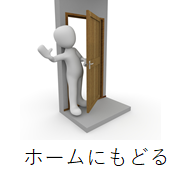トランプ関税で日本にE10ガソリンが導入される
4月2日(現地時間)米国のトランプ大統領は米国への輸入について、ほぼすべての国に高率の関税を課すと発表した。日本からの輸入品に対しては24%という高率の関税である。(今のところ一部を除いて、この新規の関税は90日間、一時停止されている。この停止期間中の交渉次第で関税率は修正される可能性がある)
このトランプ関税、さまざまなところに影響を及ぼすが、その影響のひとつとして日本にE10ガソリンが導入される可能性がある。
E10ガソリンとはバイオエタノールを10%添加したガソリンのことだ。日本で売られるガソリンには、バイオエタノールがほとんど含まれていないが、トランプ関税のおかげで、日本で売られているほぼすべてのガソリンがバイオエタノール入りになり、さらには近い将来、添加量が20%まで引き上げられる可能性もある。
これは、トランプ関税が輸出業者だけでなく一般の人たちにおよぼす身近な影響である。どうしてこのようなことになるのだろうか。
トランプ大統領が日本に高額の関税をかけるのは、日本が米国製品に対して、見えない関税を課しているから不公平だというのが理由だが、その根拠はあいまいだ。単に対日貿易赤字が大きいから、これは非関税障壁という目に見えない関税をかけているに違いないと言いがかりをつけているに過ぎない。
もちろん、これは米国側でも解っていることだろう。いろいろ理屈をつけているが、結局、目的は貿易赤字を小さくしたいということだ。このトランプ関税に対して中国やカナダ、EUなどは逆関税を米国製品に対してかけるという対抗策を早速発表している。
しかし、逆関税は日本のやり方ではない。日本はどうするか。米国の本音は貿易赤字を小さくしたいということなのだから、それなら、米国への輸出を減らすか、米国からの輸入を増やせばいいということだ。しかし、米国への輸出は減らしたくないから、結局、米国からの輸入を増やそうという話に落ち着くことになるだろう。
政府はすでに検討に入っていた?
問題は米国から何を輸入するのか、そもそも輸入するものはあるのかということだ。そのひとつとしてバイオエタノールが考えられる。というか、すでに昨年あたりから日本政府はその検討に入っていたようなのだ。
今年2月に石破首相が訪米して行われたトランプ大統領との会談では、アラスカのLNG開発が話題になったが、実はこのとき石破首相はバイオエタノールの輸入についても大統領に提案している。
トランプ大統領はこの話を受けて、「米国の農家たちは喜んでそれを提供できるだろう」と述べたという。バイオエタノールは米国のコーンベルトと呼ばれる大穀物地帯で生産されるトウモロコシを原料として作られているからだ。
米国のトウモロコシの大輸出先は中国であるが、その中国がトランプ関税に対抗してトウモロコシに大きな報復関税をかけると発表している。だとすると米国のトウモロコシは輸出量が減って大幅に余剰となる。だから日本がバイオエタノールを大量に輸入してくれるなら、これは渡りに船。米国農家にとって朗報となるだろう。
では日本に輸入されたバイオエタノールはどう使われるのか。それはガソリンに混ぜて自動車燃料として使われることになる。つまり日本にE10ガソリンが導入されるという話につながるのである。
実はその前触れがあった。昨年11月、経済産業省はE10ガソリンの国内販売を2030年までに開始し、将来はその混合割合を20%にするという方針を明らかにした。さらに、今年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画でもE10ガソリンについて同様の目標が記述されている。これは前回の第6次基本計画にはまったくなかった話だ。
つまり、政府内ではE10ガソリンの導入について、昨年後半あたりから急遽準備を進めていたのだ。政府はトランプ関税を見越して米国からの輸入増加の検討を始めていたということであろうか。
日本の年間ガソリン販売量は4,450万キロリットル(2023年度)。仮にそのすべてに10%のバイオエタノールを混合するなら、単純計算でバイオエタノールの輸入量は年間445万キロリットルということになる。バイオエタノール1キロリットルあたり11,000円とすると、総額で約500億円の輸入金額となる。これはトランプ政権に対してかなりなプレゼントになるだろう。

国内産業への影響はほとんどない
一般に輸入を増やせば国内産業が打撃を受けることが多いが、バイオエタノールについてはそれがない。そこがいいところだ。
バイオエタノールを輸入してガソリンに混ぜれば、当然、その分日本で生産されるガソリンが余剰になるが、余ったガソリンはプラスチックや合成繊維など石化製品の原料として使うことができる。
日本は石化製品を製造するために大量のナフサという石油製品を海外から輸入しており、その輸入量は年間2,490万キロリットル(2023年度)もある。余ったガソリンはこのナフサの代わりに使うことになるだろう。
では今まで輸入していたナフサはどうするかというと、それは輸入量を減らせばいい。日本はナフサをサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなど主に中東の産油国から輸入している。
日本は米国へ自動車などを輸出して稼いだドルを、中東から輸入する原油やナフサの代金の支払いに充てるという関係にある。ここで米国からバイオエタノールを輸入すれば、ナフサの輸入が減り、今まで中東に支払っていたドルが不要になる。そのドルが、米国からのバイオエタノールの輸入代金として支払われることになる。
つまり、米国からバイオエタノールを大量に輸入したとしても、その分中東からのナフサの輸入が減るだけで、国内産業が影響を受けるわけではない。そして米国から自動車輸出などで稼いだドルが、バイオエタノール代金として米国に還流することになるわけだ。
これはエネルギー源の分散化、つまり政情が不安定な中東から友好国である米国へエネルギー輸入国が変わるという観点からも日本にとって都合の良いことである。
バイオエタノールをガソリンに混ぜて大丈夫か
このようにバイオエタノールを米国から輸入すれば、国内産業には影響せず、米国の貿易赤字も改善することができる。しかし、消費者目線で見た場合、バイオエタノールをガソリンに混ぜても品質的に問題ないのかという不安はあるだろう。
実は、今まで日本でもバイオエタノールはガソリンに混合されていたのだが、ただし、その混合率は平均で1%程度とわずかであり、しかもバイオエタノールはETBEという石油類似物質に転換して添加されているから、一般消費者はほとんど気づかなかった。
しかし、E10は今までのようなETBE方式とは異なって、直接混合であるから、ガソリンの品質はかなり変化する。その品質変化や対策については、すでに他の記事に述べているので参照いただきたいが、E10ガソリンは既に米国を始めとして世界中で使われているから、きちんと対策を行えば、基本的には問題はない。
今後、日本の石油会社が中心となって、バイオエタノールの輸入とE10ガソリンの製造、品質管理と販売が行われることになるが、これから具体的にどのような方法でE10ガソリンを販売していくかが、決められていくことになるだろう。
なお、バイオエタノールはカーボンニュートラル燃料だ。通常のガソリンよりもCO2排出量が60%から70%少なくなると計算されている。政府はこの点を前面に出してE10ガソリンの普及に理解を求めてくるだろう。それはそれで事実なのだが、その一方で、バイオエタノールは米国との貿易摩擦の解消という役割も持つことになるわけだ。
2025年4月10日*14
【関連記事】
バイオエタノール入り「E10ガソリン」、メリットとデメリット
E10ガソリンとガイアックスはどう違うのか
2030年までに日本のガソリンが変わる E10ガソリン導入が遅れた意外な理由
[石油の疑問] バイオガソリンはどうなった 今でも使われているが将来はE10ガソリンへの移行も?
合成燃料はまだ幕下? ガソリンからアンモニアまで自動車燃料の番付表を作ってみた