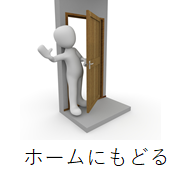国会ではガソリン税(揮発油税、地方揮発油税)の暫定税率廃止について議論されている。
ご案内のとおり、ガソリンには高率の税金がかけられている。これには本則に定められた税率と、さらにこの税率に上乗せして課されている暫定税率があり、今回の議論はこの暫定税率分を廃止しようという動きである。一方、この暫定税率廃止議論に併せて、走行距離税という新しい税金を課そうという動きがある。
暫定税率が廃止され、その代わりに走行距離税が新設された場合、これは電気自動車(EV)の普及にとって一般には逆風になると言われている。しかし、走行距離税が充電スタンドの増設などEV環境を改善するために使われるのなら、長い目でみればむしろ追い風になる。
ガソリン税は必要か
ガソリン税はもともと本則として1リットルあたり28.7円(地方揮発油税を含む)と決められている。しかし、 1974年からは道路整備計画の財源確保のためと称して「暫定的」に税率が引き上げられた。これが暫定税率の始まりである。さらにこの暫定税率は数年ごとに引き上げられ、現在のガソリン税は合計53.7円と、本則の約2倍にまで膨らんでいる。
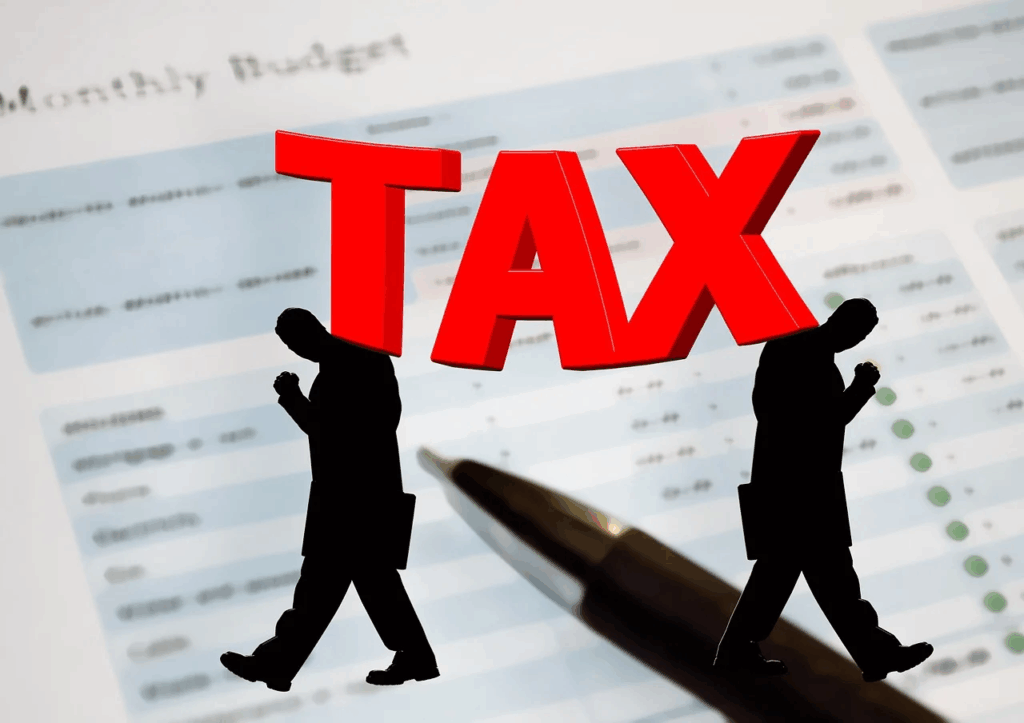
さらに、 1989年から消費税が課税されることになった。この消費税についてはガソリン本体価格だけでなく、ガソリン税の部分にも10%の消費税が課されている。つまり消費者が支払ったガソリン税自体に、さらに10%の消費税が課されているわけであるから、これはガソリン税にさらに消費税分が上乗せされたということに等しい。
このガソリン税。もともとは高度成長期、我が国の道路を整備するために設けられたものである。筆者が子供のころ(1970年代)、確かに日本の道路は酷かった。ほとんどの道路は舗装されておらず、でこぼこ道で、雨が降れば水たまりができ、日が当たれば乾燥して砂ぽこりが舞い上がっていた。これを整備・舗装するのには多額の費用がかかる。だから、道路を整備するためにガソリンに税が設けられた。
やがて日本にもモータリゼーションの波が打ち寄せ、自動車の保有台数は急激に増えていった。自動車が走るためには道路が必要。道路を整備するためには資金が必要。本則の税率だけでは足りない。だから暫定的に税金が上乗せされていったというわけだ。自動車が走るにはガソリンがいる。だからガソリンに税金をかけて資金を確保する。つまり受益者負担ということだからこれは理屈に合っているだろう。
しかしながら、バブル経済が崩壊した1990年代以降、自動車保有台数も頭打ちになってきたし、道路も整備が進み、ほとんどの道路が舗装道路に生まれ変わった。これ以上道路にお金をかける必要がないから、このまま暫定税率を続ければ税金が余るという事態になってきた。
税金が余るのなら、暫定税率を引き下げるか、廃止して本則の税率に戻すべきだろう。もともと暫定税率というのは、あくまでも暫定であり、緊急に道路整備が必要だから追加で加えた税金であって、必要なくなれば廃止しますよという意味である。
ところが、現在でも暫定税率はそのままで、余った税金は道路以外の用途に使われ始めた。そんな勝手なことをやっていいのか。おいおい、それは税金の趣旨が違うんじゃないのとだれでも思うだろう。
さらに、近年になって原油価格が高騰してガソリン価格も上昇し始めたので政府は補助金という税金をつぎ込んでガソリン価格を抑え始めた。つまり高率のガソリン税を取っておきながら、一方で税金をつぎ込んでガソリン価格を抑えようとする。
だったら、初めから税金を取らなければいい。そうすれば確実にガソリン価格は下がる。ところが税率はそのままで、その一方で税金をつぎ込んで価格を抑えようとしているのだからおバカな話だ。なぜそんな不思議なことをするのか。
ガソリン税は一部が一般財源化されたとはいっても大半は道路関係に支出されているから、道路工事事業者にとっては安定的な収入源となっている。だからガソリン税は下げられない。おそらく自民党が暫定税率の廃止にムキになって反対する理由はこれだろう。といっても、道理に合わないものは合わない。暫定税率は廃止すべきだろう。
走行距離税の導入
しかし、暫定税率を廃止する代わりに、一方で新たな税を導入する動きが出てきた。ガソリン税の大半は道路整備に充てられるわけであるが、これがなくなっても本当にいいのかという議論である。
ことし1月に起きた八潮市の大規模な道路陥没事故で分かるように、過去に作られた道路は放っておけば壊れていく。それは道路の陥没であったり、橋やトンネルの老朽化であったりする。この老朽化した道路に関連するメンテナンスの財源をどうするのかという話である。そこで導入が検討されているのが走行距離税だ。
走行距離税は車が道路を走った距離に応じて課税する仕組みである。1km走るごとにいくらという割合で課税されることになるだろう。ガソリン税は道路整備のために使われるのだから、道路の使用料のようなものである。
本来は道路使用つまり、どのくらいの距離を走ったかで課されるべきものであるが、走行距離の把握がむずかしいのでガソリンや軽油に課税されていたわけである。つまり取りやすいところから取るという徴税の原則そのものだ。
確かに、走行距離が増えるほどガソリン消費も増えるから、ガソリン税は走行距離税と同じようなものである。しかし、現在は少し事情が変わってきている。
まず、ハイブリッド車や軽自動車のように、燃費の良い車が普及してきて、走行距離とガソリン消費量が必ずしも一致しなくなってきた。さらにEVはいくら道路を走っても、まったくガソリンを使わないからガソリン税を徴収できない。
これから、燃費のいい車やEVが増えると、ガソリンから税金を取るやり方では、どんどん税収が減っていくことになる。そこで、ガソリン消費量ではなく、走行距離に応じて税金を取ったらいいんじゃないかというのが、走行距離税だ。
走行距離税はEVにとって逆風なのか
では、本題の暫定税率の廃止、走行距離税導入でEVは有利なのか不利なのかという話である。
暫定税率が廃止されると、その分ガソリンが安くなるからガソリン車が有利になる。 EVの売りのひとつは電力がガソリンより安いというところだったが、その差が縮まることになる。これはEVにとって不利だ。
さらに、走行距離税が導入された場合はどうなるか。ガソリン車にとっては走行距離税が導入されても、一方でガソリンの暫定税率が廃止になるのだから影響はそれほど大きくない。しかし、EVについては、ガソリン税の低減というメリットがないところに、走行距離税という新たな税が課されるわけであるから、明らかに不利になる。
さらに、道路補修費の捻出というのが走行距離税の趣旨なら、道路を壊すという点で、重い車ほど税率を高くすべきであるが、この点でもバッテリーを積んで重くなるEVは不利になる。
以上のように、ガソリン暫定税率が廃止になり、代わって走行距離税が導入されるならば、EVの普及にとっては基本的に逆風になる可能性が高い。
走行距離税でEVが有利になることも
一方で、 EVが有利になることもある。その大きな理由は、税金を払うことによってEVが市民権を得るということになるからだ。
EVといえども、道路を走るのだから道路補修費などを支払うのが筋である。それによってはじめてEVは公式に道路を走る権利を得ることになる。今までは、道路関連の費用はガソリン税や軽油引き取り税で賄われており、EVはいわばただ乗りの状態であったが、走行距離税が取り入れられることによってはじめて一人前と認められることになる。
これは単なる気持ちの問題ではない。一人前と認められることによってEVは国に対して権利を主張することができるのだ。
例えば、充電設備である。日本にはまだEV用の充電設備が不足しているといわれるが、国の支援によって全国に充電設備が作られればEVは格段に使いやすくなる。職場でもショッピングセンターでもあるいは月極駐車場でも、車が動いていない時間はたっぷりあるのだから、その間に充電できれば、電気切れの心配は減ってくる。
そのほかEVに関する道路行政や車両規制、研究開発などでも、EVへの配慮が行われることになるし、それに関連した予算も付きやすくなる。
今後、燃費のいい車が増え、車両の保有台数そのものも減ってくればガソリン税収はどんどん減ってくる。EVは環境にいいのは分かっているが、ガソリン税が取れないからどんどん普及されても困る。
そんなとき、EVからでも税金が取れるとなれば、国にとっては渡りに船。EVはガソリン税に代わって国や地方自治体のドル箱になるだろう。国はEV普及に向けて積極的な政策を打ち出しやすくなる。この効果は相当大きいと考えるべきなのだ。
2025年9月9日
【関連記事】
電気自動車のCO2排出量はガソリン車の約半分 2050年には4分の1になる
日本のガソリン車が全てEVに代わると、日本の電力需要はどれだけ増えるのか
EV販売台数は各国のCAFE規制によって決まる 日本でEVが売れないのはCAFE規制のせい
電気自動車(EV)界のゲームチェンジャー全固体電池とは何か 5分で解説
日本こそEV化を推進すべき3つの理由(1) 全固体電池
EV(電気自動車)はエコじゃない? ネット知識は間違いだらけ
天下の悪税wwガソリン税 EV普及でどうなる EVは本当にガソリンより経済的か?