CO2を分解することはできるのか
CO2を分解して「脱炭素」できそうなのに、進まないのはなぜ? と称する記事が先日、東京新聞に載った。
「二酸化炭素(CO2)を炭素(C)と酸素(02)に分解する方法がまだ一般的でないのは、技術的な問題かコスト的な問題か、どちらでしょうか」という質問に対して、北海道大学のある名誉教授が行った研究を紹介。その研究によると、電気分解装置によってCO2を炭素と酸素に分解できることが実証されたという。
「だったら、空気中のCO2を分解してしまえば気候変動対策は簡単にできてしまう」ということになるのだろうか。
この記事では、CO2の分解は技術的には問題はなく、どちらかというと、コスト的な問題。それを克服して実用化しようと研究が進められてきた。と述べている。
つまり、技術開発が進んでコストを低減できれば、空気中のCO2を分解して脱炭素をすることができるということになりそうだと期待を抱かせる。しかし実はそうはいかない。この新聞が言うように技術やコストで解決できるということとは違った、できない理由があるのだ。
CO2を分解しようとすると、かえってCO2が増えてしまう
まず、 CO2は非常に安定な物質だ。だからこれを分解しようとすると大きなエネルギーが必要となる。これを達成するのが北大の名誉教授が行った電気分解だ。電気というエネルギーを与えてCO2を分解する。その分解に必要なエネルギーはCO2、1モル(44g)当たり393.51kJ。つまり、44gのCO2を電気分解するには393.51kJ分の電力が消費されることとなる。これは自然の法則なので変えられない。
一方、この電力を発電効率40%のLNG火力発電所から供給しようとすると983.75kJ分のエネルギーが必要となる。このエネルギーをLNG(主成分はメタン)の燃焼によって得ようとすると、メタン1モルの燃焼エネルギーが890.40kJだから、1.10モルのメタンを燃やさなければならないことになる。
1.10モルのメタンが燃えると、同じく1.10モル(48.4g)のCO2が発生するから、つまり電気分解法でCO2を分解しようとすると、火力発電所でその1.1倍のCO2が発生することになるのだ。
なお、ここではCO2を電気分解する装置の分解効率を100%として計算しているが、実際には100%よりずいぶん小さくなると予想されるので、必要な電力はもっと多くなる。だから、火力発電所で発生するCO2はさらに増えることになる。
ごちゃごちゃと計算をしたが、言いたいことは、CO2を分解することはできるが、そのために大量の電力が必要となり、その電力を火力発電所で作ろうとすると、火力発電所で大量のCO2が発生する。その結果、分解するCO2より発生するCO2の方が多くなってしまうということである。
これはコストや技術の問題ではなく、物理学の問題であり、いくらコストを低減しても、あるいは技術が進歩しても解決は不可能なのだ。
再生可能電力を使ったらどうか
以上の計算はCO2を分解する電力をつくるために火力発電を使ったが、そうではなく太陽光や風力のような再生可能エネルギーを使えばいいのではないかという反論もあるだろう。この場合はCO2を電力で分解しても、その電力を作るときにCO2が発生しない。しかし、これはまずいやり方である。
再生可能エネルギーがそんなに豊富にあるのなら、それで家庭や工場で使う電力需要をまかない、その分、火力発電で燃やすLNGや石炭の量を減らすべきだろう。そうすれば、その分CO2の発生量が減ってくることになる。
つまり再生可能エネルギーでCO2を分解するくらいなら、その分、火力発電を減らした方がいいということである。その方がわざわざ再生可能エネルギーを使ってCO2を分解するよりずっと効率的である。
風邪をひいてから風邪薬を飲むくらいなら、最初から風邪をひかない方がいいに決まっている。それと同じでCO2を発生させてから、 CO2を電気で分解するより、そもそもCO2を発生しない発電は一般需要のために活用すべきだということだ。
CO2の直接分解が有効になる使い方
ではCO2を直接分解するというアイデアは役に立たないのだろうか。
実は、筆者はここまで筆を進めてから、このCO2を直接分解する方法を活用するあるアイデアを思い付いた。単に空気中のCO2を分解してCO2濃度を減らして温暖化を防ごうというのは、結局、電力を使うので却ってCO2を増やしてしまう。あるいはそんな電力があるのなら他の用途に使えばいい。しかし、CO2の直接分解法は、うまく使えば役に立つやり方がある。
このアイデアについては、もう少し考えをまとめて、改めて紹介したい。
2025年2月5日


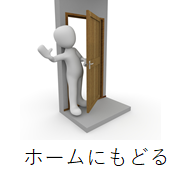
“夢のエネルギー”実用化目指し「人工光合成」検討会設置
環境省(2025年5月13日)
テレビ朝日系列ANNnewsCHから
「世界に先駆けてモデルを構築する、まさにオールジャパンで取り組んでいくという気概で取り組んでいきたい」
と、浅尾環境大臣のコメント
人工光合成もいろいろあって、脱炭素、二酸化炭素を分解して有効活用から、水素社会など気体、じゃなくて期待はされていますが、
やっぱり夢のエネルギーになりそうな予感が。
2年前の大阪、ドリーム燃料が懐かしい。
最近のニュースからさん コメントありがとうございます。
環境省は人工光合成に関する検討会を開催したと報道されていますが、その議事録がまだ公開されていないようなので、内容がよくわかりません。
光合成とは太陽光エネルギーを使ってCO2と水から有機物を作り出す。いわば空中炭素を有機物として固定する技術で、これが人工的に行えれば、地球温暖化対策の一つとして期待されるところです。
ただ、今の研究は空気中のCO2ではなく、化石燃料を燃やして出てくるCO2が使われているので生成した有機物を燃やせば、結局空気中のCO2を増やしてしまいます。また、光触媒を使って水から水素を作り出す方法も光合成といわれていますが、これは光「合成」ではなく光「分解」というべきでしょう。この場合は太陽電池で発電して水を電気分解する場合とどちらが効率がいいかという話になると思います。
人工光合成については、単なる夢で終わらずに、なにか画期的な成果が出ることを期待したいところです。
2年前に、ここのサイトでも盛り上がっていた、
大阪府や大阪市、さらに大阪商工会議所にテレビ大阪のやさしいニュースでも取り上げた人工石油、改めドリーム燃料ですが。
どうやら少しだけ形を変えて、今度は大阪の泉大津市で問題になっているようです。
今月3日の木曜日に、泉大津市の助松公園で合成燃料の実証実験を行い、その様子を市長がSNSで発信したところ、数字がおかしいとネットが炎上。
ここでは合成燃料となっていますが、以前の人工石油、ドリーム燃料と同じで、登場人物も以前と同じ仙台の会社。
今回は、名誉教授は出てこず、代わって大阪の有限会社の会長さんが。
長くなりそうなので、産経新聞が今回の件や2年前の話、さらにエネオスの話まで、ちょっと長いですが上手くまとまっているようで、そちらをどうぞ。
やっと、この件の決着がつきそうで。ヤレヤレ。
今度は合成燃料さん 情報提供ありがとうございます。
今回は元京大教授のドリーム燃料ではなくて、元教授と喧嘩別れしたサステナブルエネルギー開発が後ろでやっているようです。IT media Newsの記事ではサステナブルエネルギー社の見解が記載されています。これによると高効率UVライト(LED)は反応のエネルギー源ではなく、活性化エネルギーを付与するもので、反応のエネルギー源はCO2と炭化水素が反応するときに自ら発熱して出てくると説明してます。しかし、そもそもこの反応は水が分解してできる水素とCO2が反応して炭化水素ができるFT反応だったはずですから、サステナブル社の説明は反応自体が違ってきています。またCO2と炭化水素が反応するというのなら炭素鎖が長くなるはずで、種油と同じものができた(できたように見えた)という当初の実験結果とは違ってきます。サステナブル社の説明はいろいろと不可解です。