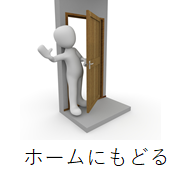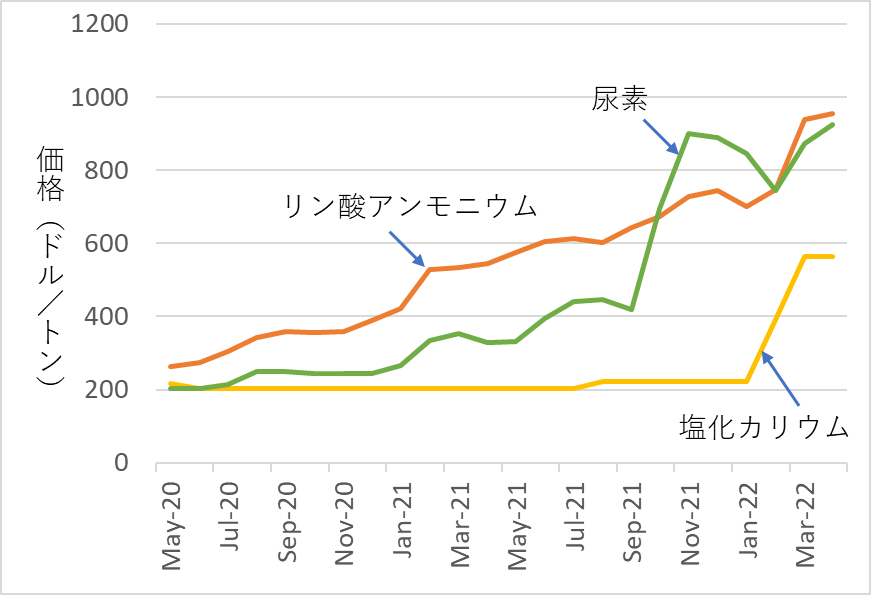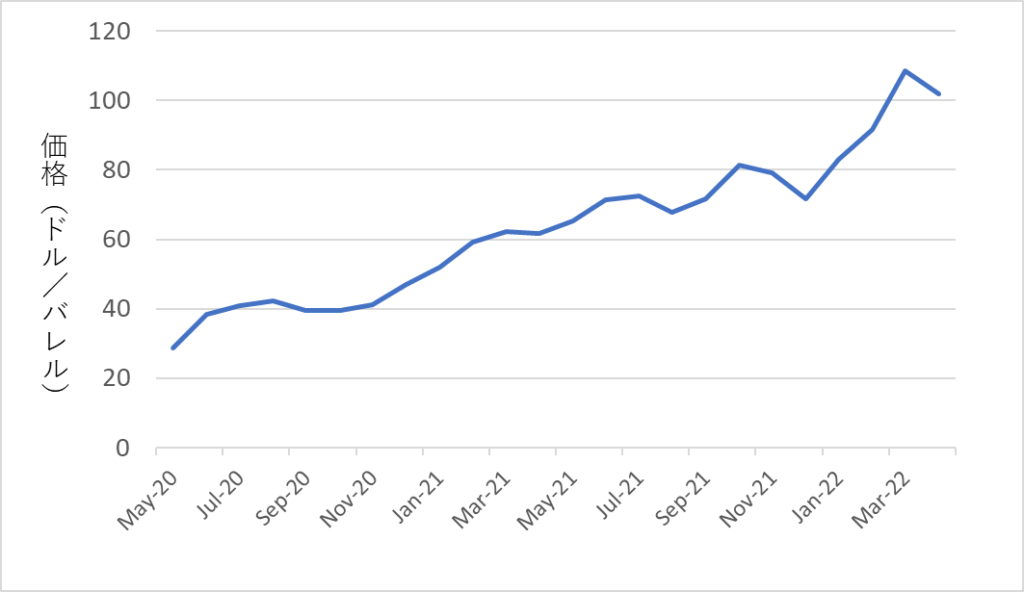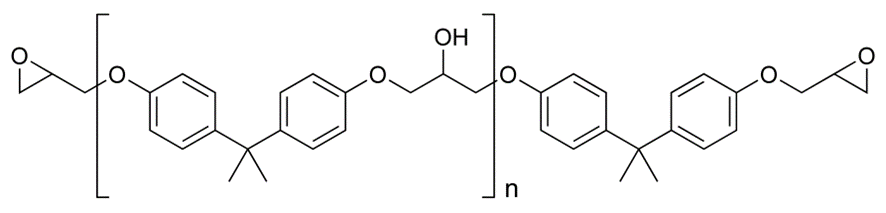私の書いた記事がオルタナ誌やヤフーで公開されるようになり、この記事を読まれた方々からコメントや質問をいただくようになりました。これらのコメントや質問は大変役に立つ、ありがたい物ですが、中には私の記事がよく理解されていないのではないかと思われるものもあり、これも私の表現力の拙さであると反省しています。
そのような記事のひとつ「ブレーキが2つでも暴走、原発は根本的に「危険」と断言する理由」として紹介された記事について、つぎのようなコメントをいただきました。
「記事では冷却水をブレーキといっているが、冷却水の働きで中性子を減速して核反応を起こりやすくしているのだからブレーキではなくアクセルである。冷却水がなくなれば核反応は起こりにくくなり、核反応は止まってブレーキとして働く」
お前はそんなことも知らないのかと言わんばかりのコメントでしたが、いえいえそんなことは知っています。確かに、水は中性子を減速して核反応を起こさせるのでアクセルです。しかし、このアクセルを使って実際に原子力発電所をコントロールしているかといえば、そうではありません。
核燃料は冷却水の中に完全に浸かっていて、その冷却水が中性子を減速する働きをしていますが、その量を増減させて核反応をコントロールしているわけではありません。いわば、アクセルを踏みっぱなしの状態なのです。
で、そのままでは原子炉は暴走してしまいますから、制御棒で中性子の量をコントロールし、発生した熱を冷却水で運び去っているわけです。コメントのように冷却水は核反応を抑えるブレーキとして働いているわけではありませんが、発電所というシステムが暴走しないように実質的にブレーキとして働いているということをこの記事の中では指摘しているわけです。
火力発電所なら、燃やす燃料の量によって、出力をコントロールすることができるわけですが、原子力発電所の場合は、燃料と減速材が余剰に充填されていて、その量を調整することをしていません。
だから、その出力は減速材で調整し、さらに発生した熱で原子炉が過熱しないように冷却水で冷却しているのです。つまり、アクセルをいっぱいに踏みながら、同時にブレーキを踏んで速度をコントロールする仕組みになっているわけです。
原子力発電所の放射能漏れや核廃棄物の処分の問題についてはいろいろと議論されていますが、原子力発電所の運転特性について解説したものはあまりみかけません。
この記事では核反応そのものではなく、核反応で発生したエネルギーを発電に結びつける原子力発電所の制御について、常に暴走の危険があり、誰かが常にブレーキを踏んでいなければならないという特殊な制御を行っているという危険性を指摘しているのです。
数日前から、欧州最大といわれるウクライナのザポリージャ原発に砲撃やミサイル攻撃か行われていると報道されています。これが火力や水力発電所なら、運転員はさっさと退去して発電所は放棄してしまえばいいこと。発電所は勝手に止まってくれるでしょう。
しかし、原子力発電所はそうではありません。常に誰がブレーキをかけていなければならないのです。特に冷却水を喪失すれば核反応自体は停止に向かいますが、核燃料内の放射性崩壊によって熱が発生し続けます。その結果、炉内が熱で溶解し、また水素爆発を起こして、放射性物質を広範囲にまき散らしてしまうでしょう。
そうなれば、おそらく半径数10km、下手すれば100㎞以内にはロシア軍も、ウクライナ軍も、住民もだれも立ち入ることができなくなる可能性があるのです。
原子力発電所の最大の問題点はこのような大災害につながる危険性をはらみながら、常に誰かがブレーキを踏み続けなければ暴走してしまうという運転方法を取っているということです。
その結果、ザポリージャ発電所は、そこが戦場になってしまったにも拘らず、運転員は避難することができません。命をかけて操業を維持しなければ、大災害に結び付いてしまうのです。これがザポリージャ発電所の置かれた状況なのです。
2022年8月18日
【関連記事】
核融合発電は「クリーンで無尽蔵で安全」ではない 実用化にはいまだに高い壁
原子力発電のここが危険 ブレーキを踏み続けなければ暴走するシステム
アンモニア発電…マスコミが報道しない問題点 このままではかえって温室効果ガスが増えてしまう
ブログ記事「アンモニア発電…マスコミが報道しない問題点」へのご批判について
福島第一原発のトリチウム汚染水問題